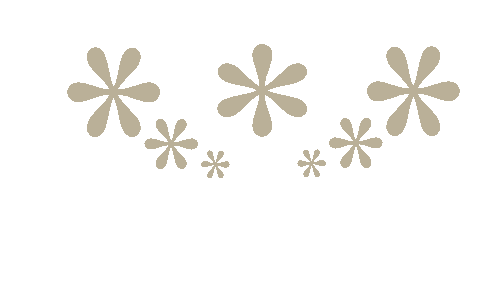
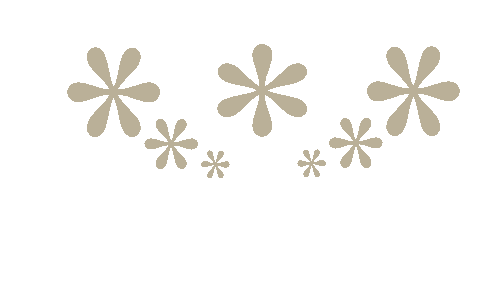
| きっと、忘れられない 五月四日、というこの日を…… 「で、本当の所はどうなんだよ?」 放課後、新一はいつも通り蘭の部活が終わるのを教室で待っていた。これから新しい推理小説でも読もう、としたときだ。クラスの数人の男子が、こぞって新一に訊いてきたのは……。 「あのなぁ、んなことテメーらに関係ねぇだろ」 新一は持っていた小説に視線を落として、この話はお終いだと行動で示す、がそれで納得する高校生男子ではない。 「でもさ、告白したんだろ?」 「そうすればやっぱり、なぁ」 「そうそう、あの毛利と……って健全な男なら考えちまうわけよ」 (んなもん、考えるな) 新一はジロっと睨みつけ、 「テメーら、人の恋路よりテメーの心配したらどうだ」 「!」 瞬時に息をのむ男子たち。 それぞれ思うところがあるのだろう。しかし、やはり他人のあんな事やこんな事が気になるお年頃。新一のそんな一言では引き下がれるはずもない。 「だってよー、ずっと『幼馴染み』だったわけじゃん、いざキスしようとしても、さ」 「そうそう、お前らってすでに夫婦みたいなもんだし」 「知らねぇやつにするより大変かなって……心配になっているわけよ」 (こいつら……) 新一は開いていた小説をパシッと閉じて、三バカコンビに視線を上げる。 「聞きてーなら、いくらでもテメーらの弱みを並び立ててやるぜ」 新一の瞳が、鋭利な刃物のように彼らを突き刺す。 「ぐッ!」 容赦のない新一の双眸に、さすがの彼らも黙って、そしてそそくさと教室を出て行った。 「ったく」 新一は溜息をついて、彼らの出て行った教室の戸を見つめる。不意に再度その戸が開かれて、 「お前も難儀だよなぁ」 と苦笑交じりの声が届いた。 「葉月」 「やっとあの事件から解放された、と思ったら今度は毛利との恋愛沙汰か……話題が絶えない奴だよな。お前って」 葉月と呼ばれた青年は、新一の悪友とも呼べる、言うならば蘭で言うところの『園子』みたいな男だった。 高校になってクラスが違う事もあって、互いに行き来も少なくなったが、小学校時代からの腐れ縁、という間柄で、付き合いが長いこともあって園子同様、新一に好き放題いえる数少ない男だった。 「なんだよ。テメーも蘭とオレの……」 「今更んなもん聞いてもな。テメェらの進展度なんぞ興味もねぇよ。成るように成った。それだけだろ」 「じゃ、何しに来たんだよ。2―Fはずっと端だろぉが」 新一は2―Bで葉月は2―Fのクラスだった。 「なあーに、ちょっとした息抜きさ」 「はあぁ?」 「モテ過ぎるのも、問題だよな」 いけしゃあしゃあとそう言って、葉月は口元を歪める。 「テメー……由香にその良く回る口、縫い止めてもらえ」 由香、とは葉月の恋人で、蘭や園子の小学校時代からの親友である。高校が違う事もあってあまり会うこともないらしいが、少なくとも中学までは同じ学校に通い、その頃からこの厚顔無恥男と付き合っているのだ。 「行き過ぎれば、ちゃんと塞がれるさ」 葉月の含みを帯びた笑いが、新一に向けられる。咄嗟に何のことかわからず眼を見張る新一だが、すぐに合点がいき、 「オメーなぁ…」 と力なく項垂れた。 由香とのキスを仄めかす葉月に、さすがの新一もそれ以上何も言えず、ただ肩を落とす。 (よくこんな男と付き合えるな、由香は…) 深く溜息を吐き、そこにはいない由香に同情する。とはいえ、葉月は決して軽薄な男ではない。彼にとって彼女がどれほど大切かは、十分すぎるほど知っていた。 そう、自分が蘭を大切に思っているのと同じように。 そして新一はある事を思い出した。 かつて、まだ新一たちが中学のときのことだ。あれは確か、葉月と由香のファーストキスがどうとか、という話題を園子が持ち出したときだった。 『次は蘭と新一君だね』と誰憚ることなく園子がそう言って、 『園子ッ!』 『バーロッ!』 と二人同時に詰め寄り、そして蘭と由香は頬を赤く染めながら園子の背を押しその場からいなくなった。その後、 『新一、お前も毛利とキスしたら、ちゃんと知らせろよ……』 めったに見せない羞恥に染まった真っ赤な顔で、葉月は新一を睨みつけ、 『その時は、俺らの番だからな』 番、というのは、園子と蘭と新一の三人が葉月と由香のファーストキス祝い、ということで目論んだ、内輪なパーティのことだった。別名冷やかし談話、とも言う。 しかし新一はただ黙って聞いていただけで、別に彼らを冷やかした覚えなどない。主に話を盛り上げていたのは、言うまでもなく、園子一人だった。 新一は不意に浮かんだあの頃の記憶に、葉月の顔をチラッと見、そんな新一の思考を読んだのか、葉月がにこりっと微笑んだ。口元に浮かぶ含みを帯びたそれに、新一はずんと肩を落とし、そして敵わないと思いながらもポーカーフェイスを取り繕って、 「オレは、言わねーからな」 「約束を違えるつもりかよ」 葉月の笑みが消える。 「ぜってーに、言わねー」 新一は素早く席を立ち、葉月に背を向けた。 「だいたい、蘭はそういうことに人一倍疎いんだ。んなもん待ってる奴の気が知れねーよ」 自分のことは棚にあげ、新一はそう言うと、颯爽と葉月の脇を通り抜け、そして教室を後にした。 一人教室に残された葉月は、ポカンとその後ろ姿を見つめ、そしてその後ろに続くもう一つの影に、クスっと笑みをもらした。 「ほんと、難儀な奴だよ……テメーのことには、とことん疎いんだからな」 「蘭、もう新一君へのプレゼントは決まったの?」 新一の誕生日を二日後に控えたその日、蘭と園子はショッピングを堪能した後、日当たりのいいカフェテリアに入って、ティータイムを設けていた。そして聞きたくてうずうずしていたのだろう、園子はぐいっと蘭に顔を近づけ、そう尋ねた。 何かを期待したような園子の表情に、蘭はその意図には気づかぬまま、 「うん、とりあえず、お豆腐のお味噌汁かな」 と答えた。 「え……」 蘭の思っても見なかった返事に、園子はそれ以上の言葉をなくし、固まった。 ―豆腐の味噌汁…… 自分の聞き間違い?とも思ったが、蘭は確かにそう言った。 刹那、 「何考えてるのよぉ―ッ!」と店内に響き渡るかのような大声を張り上げ、がしっと蘭の両肩を掴んだ。 「違うでしょ!あんた達恋人同士なのよぉ!恋人同士!!なのにお味噌汁って……ふつうはワインとかカクテルとか、もっと気の利いた―」 すごい勢いで捲くし立てる園子に、一気に店内の視線が集まる、がそんな事を気にする彼女ではなかった。 「っていうより、キスでしょ、キスっ!」 瞬間、言っている園子より、言われている蘭の方が慌てて、彼女の口を押さえた。 しかしその瞳はまだ言い足りない、というふうで、怖いぐらいに大きく見開かれている。 「お願いだから……」 真っ赤に頬を染めながら、蘭は園子に祈るような視線を向けた。 それにはさすがの園子も、少し落ち着きを取り戻し、肩から力を抜く。が蘭の肩に置いた両手をそのままに、 「で、どこをどう間違えたら、お豆腐のお味噌汁、が登場するわけ」 園子はじっと蘭を見据え、その訳を決して聞き逃すまいと耳を傾けた。 すでに彼女の中には、期待を通り越して、確定になっていた、蘭と新一のファーストキス。 数ヶ月前、やっと幼馴染みから卒業し、恋人同士になった蘭と新一。しかし傍から見てもなんら進展どころか、変わった様子のない二人。 ここで一発キスでもすれば……と思うのは二人をずっと見てきた園子だけでなく、クラス中の誰もが思っている事だった。 キスの一つでもすれば、もっと親密度が上がり、はれて『恋人同士』という呼び名に相応しくなるに違いない、と。 事実、ずっと二人を見てきた園子にとってすれば、とてつもなく歯痒くもあり、また面白くないのである。 恋人同士になったんだから、もっとラブラブモードになってもらわなければ、からかう楽しみが半減してしまうというものだ。 新一から告白された、と蘭が園子に打ち明けてくれた当初は、からかいのネタに事欠かなかったが、さすがに数ヶ月も経てばネタも尽き、からかうこと自体面白くなくなってしまう。 だからこそ、今度の『新一の誕生日』に賭けたのだ。 少しぐらい進展して、あわよくば、ファーストキスぐらい奪えるかも……と。 しかしだ。 当の本人たちは― 「だからね。今回は新一の欲しいものでもあげようかなって思って……」 蘭は園子の様子に、ことの経緯を話し出した。 『五月三日、ちゃんと空けといてよ』 放課後、部活を終えた蘭は、自分を待っていてくれた新一に、毎年繰り返しているだろう言葉を告げた。 『五月三日……憲法記念日がどうかしたのか?』 『はあぁ……五月四日は新一の誕生日でしょ!まったく、毎年毎年、どうして自分のことなのに忘れられるの?ほんと、自分のことには無頓着なんだから……』 溜息を吐きながら、蘭はまたも毎年恒例の言葉を紡ぐ。 『私が気づかせないと、ほんと無駄に年取っていくわね、新一は』 『別に、誕生日なんて……』 『そう。せっかく今年は新一の意見も取り入れて、とか思っていたのに』 『はあ?』 『新一、今欲しいものある?』 『欲しいもの?』 『うん、ほら毎年新一へのプレゼントは私が勝手に決めてるでしょ。だから今年は趣向を変えて、新一の欲しいものを用意しようと思って。欲しいものなら、少しでも新一の心に残るでしょ』 そう言って笑う蘭に、新一は僅かに口元を綻ばせる。 蘭からもらったものは、全て大事に使わせてもらっている。ただ、蘭の前では見せないだけで。 『で、欲しいものある?お金には上限ありだけど、出来る限り副うつもりだから……』 こんな時、ふざけてでも『蘭が欲しい』とでも言えればいいのだが、新一にはそんな真似などできるはずもない。 『そうだな……』 少し考えて、そして、 『和食、かな』 『えっ?』 『この所店屋物ばかりなんだよ。炊き立てのごはんに、作り立ての味噌汁……が欲しいかな』 コナンだったときには当たり前の夕食。 もし、工藤新一に戻った事に一つ不満を言うとすれば、それは蘭の手料理を毎日食べられなくなったことだろうか。 コナンであったときは、あまりに当たり前すぎて思いもしなかったが。工藤新一戻って、一人であの家に住み、家事をする事がどれだけ面倒で、一人だけの食事がどれほど空しいものなのか、つくづく思い知らされた。 コナンになることが出来なければ、きっと思いも寄らなかったことだったに違いない。そういうものなんだ、と思って過ごしたことだろう。 だからこそ、今新一が一番欲しいものは、蘭の手料理であり、蘭の存在、そのものだった。 『ホント?本当に、そんなものでいいの?』 新一の答えに、蘭は驚いたように瞳を見開く。 『ああ。欲しいものって言ってもそうそう一つに絞れねぇし、今はそれが一番欲しい、かな』 『店屋物って……、新一ちゃんとご飯食べなきゃ』 『しゃーねーだろ。自分でやるのが面倒なんだよ』 新一とて料理が出来ないわけではない、いや、男にしてはそこそこに出来るほうだと、自負している。しかし一人で作って、それを一人で食べることに、僅かな空しさを感じてしまったのだ。 『とにかく、プレゼントは和食でいいぜ』 『和食って、おかずは?なんかリクエストないの?』 『そうだな……』 新一は少し考えて、そして結局、 『何でもいいよ。作り立てなら……』 と答えた。 欲しいのは蘭の手料理で、蘭が作るものなら、何でもよかった。エプロン姿の蘭の背中を見ることが出来るなら……あのときのように、その横で皿を出すのも、きっと悪くない、と新一は小さく微笑んだ。 そして、蘭は新一に、和食をプレゼントすることになった。さしずめ、お豆腐の味噌汁と炊き立てのご飯。でもまだおかずが決まっていない。 と、蘭は園子に告げる。 「それじゃ、お母さんじゃない……」 刹那、園子は首を振って、大きく溜息を吐いた。 「何が悲しくて、恋人のバースディに、和食をプレゼントしなきゃならないのよぉ……新一君も新一君だわ。プレゼントの催促が、和食……せめてフレンチとか……」 「そんな、フレンチなんて私の方が困っちゃうじゃない」 「でもねぇ、だって恋人の誕生日なのよ。『こ・い・び・と』のよ!」 またも園子の声が音量を増し始める。 「恋人のバースディって言ったら、大切な人が生まれた奇跡の日よ!クリスマスやニューイヤーとかとはわけが違うのよ!恋人のバースディは一番大事なビッグイベントなのよ!それなのに、それなのに……」 園子はよろよろと力なくテーブルにうつ伏せ、 「なんでお味噌汁なのぉ!!」 と大げさに嘆いた。 「そんなに変、かな?」 蘭はそんな園子に、小さく呟きを漏らす。 実際、初め新一に『和食』と言われたときは蘭自身驚いたが、考えてみると、自分の手料理を欲しい、と言うことで。 そう思えば、もしかしたら一番良い形のプレゼントのような気がして、蘭もあれやこれやとおかずを考えるのが、楽しくなり始めていた。 『和食』というからにはやはり魚料理かな、とか、それとも天ぷら?とか、お袋の味ならやっぱり肉じゃが?とか、挙げられるだけの和食を挙げて、偶に脱線して、ハンバーグって和食じゃないよね、とか思いながら、必死で新一のプレゼントを考えている自分に、結局、今年も同じように悩んでいる、とか。そんな自分が妙に恥ずかしく、そしてそんな毎年が、これからもずっと続けば良い……と思った。 毎年、こうやって、新一へのプレゼントに悩む自分、そんな自分が積み重なって、そしてずっと……。 蘭は気恥ずかしげに、その顔に笑みを浮かべた。 そんな蘭に、もはや何も言えない園子は、 「和食だったら、やっぱり肉じゃがは外せないわよね」 と溜息混じりに意見を述べる。 「マジ、うめーよ」 新一は出された全てのものに箸をつけ、それを一つ、また一つと終わらせていく。 炊き立てのご飯に、豆腐の味噌汁。そして肉じゃがに、鯖の竜田揚げ。あとは海老と水菜の煮浸し。 魚料理と肉料理をあわせ、それに店屋物しか食べていないと言っていた新一の事を考えて、少しでも温野菜を、と思いお浸しを加え。 「和食って素朴だけど、すぐに上手下手がわかるんだよね。出汁のとり方だって工夫してあるんだから……もう少し味わって食べてよ」 次から次へと殻になっていく器に、蘭は溜息を吐いた。しかしその瞳が裏切っている。それもそのはず、好きな人が自分の料理を美味しい、と言って食べてくれるのは、やはり女の子なら一番の幸せの時だろう。 出したものをちゃんと食べてくれる、というのもまたしかりだ。 そして、恋人の幸せそうな顔。 蘭はその口元に笑みを浮かべ、じっとそんな新一を見ていた。 「んっ?オメーも早く食べろよ。冷めちまうぞ」 そんな蘭の心情などお構い無しの、新一の態度に、一層蘭は微笑んで、自分も箸をつけ、新一との久しぶりの夕食を楽しんだ。 新一の誕生日まで、あと数時間。 (まだ五月三日なんだよ……新一) 蘭は新一をチラッと見つめ、心の中で呟いた。 新一へのプレゼント、『和食』は前菜でしかない。 メインディッシュは…… 蘭は厳かに唇を引き結び、今また時計を仰ぎ見る。 (あと、二時間四十二分……) 今日何度目かの蘭の仕草。 新一は気づいてはいたが、それについて指摘することを意図的に避けた。 恐らくは、十二時になった瞬間、「オメデトウ、新一」といつもの笑顔で言うつもりなのだろう、と。 だからこそ、 「蘭、コーヒーでも淹れようか?」 と間を考えて蘭に声をかける。 もちろん、 「私が淹れるから、新一は座ってて」と返事が返ってくることを見越して。 時計の針が進むごとに、落ち着かなくなる蘭。そんな彼女に思わず微笑んで、新一はその後ろ姿を見つめた。 コナンの時には見慣れていたはずのその姿に、未来予想図ともいえる、ある映像が反映されて……。 そしてつい先日の、葉月との会話を思い出し。 (ファースト、キスか……) じっと見つめた蘭から、不意に覗くその唇に、新一は慌てて視線を逸らした。 新一とて、そういう欲望がないわけでは決してないが、蘭のことを考えると、自然、 (急ぐことなんてねーよな……)と思えてくるから不思議である。 きっとコナンであった時がそうさせるのだろう、と思った。 コナンとして過ごした蘭との時間。歯痒くて、苦しくて、身動きできないでいたあの頃、それでもたった一つ、蘭は自分を待っていてくれる……それだけで十分だと思えた。 形のない気持ち、それが新一にはしっかりとみえたから。 (ゆっくりでいいからよ、いつかキスさせてくれよな、蘭) 新一はその後ろ姿に、そっと呟きをもらした。 そして、五月四日。 午前零時。 「新一……」 蘭の顔が近づいて、 「―お誕生日おめでとう」 伏せられる瞳、 そして、重ねられる唇。 「葉月君にはナイショね」 そう言って笑った蘭の顔を、きっと忘れることは出来ない。 そう、五月四日という『特別な日』を…… |